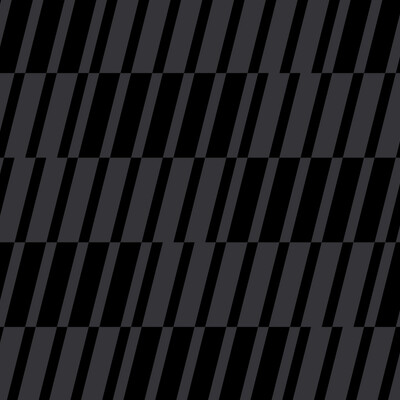MUTEK.JPは、「バックグランドストーリーズ」と題するエディトリアルシリーズを新たにスタートします。このシリーズでは、過去のフェスティバルで収録されたパフォーマンス映像をアーティストのインタビューとともに公開。演奏 / 上演された作品の背景にあるアイデアやインスピレーション、テクニカル面などについての裏話を訊きながら作品を振り返り、アーティストに改めてスポットライトを当てることを目的としてます。
本シリーズの第一弾アーティストは、JACKSON kaki。多作な新進気鋭のニューメディアアーティストである彼は、VR/AR/MR、映像、ゲーム、インスタレーション、サウンドアート、3DCGなどを用い、カウンターカルチャーの視点でポストインターネット世界に問うディストピア仮想領域と批評的言説で知られます。
2021年12月に渋谷で開催された第6回目MUTEK.JPフェスティバルでJACKSON kakiは、仮想空間と現実空間の間のトワイライトゾーンをスマートに表現したステージベースのオーディオビジュアルパフォーマンス『存在している』を発表しました。マルチなプロデュース力が示されたこの作品で彼は、VRとオーディオビジュアルライブパフォーマンスを融合させ、実験的なサウンドの響きを加えながら、物理的世界における人間としての存在といわゆるメタバースにおけるアバターとしての存在の関係性に取り組んでいます。そのようにして、JACKSON kakiは個人的な考察や経験に基づいた、不穏でありながら力強いナラティブを持つ「メタ・シアター」作品を観客に提供しました。
そんな彼にパフォーマンスについて話を訊きました。30分のパフォーマンス映像と合わせて、インタビューを以下にご紹介します。

↑(画像をクリックするとパフォーマンス映像がスタートします)
この前のパフォーマンスについて詳しく教えてください。
MUTEK.JP 2021で披露した作品について、以下のように紹介しています。
タイトル:『存在している』
この作品はバーチャルリアリティを活用した没入型のゲームアート作品であり、その発表形式としてパフォーマンスを採用する。このゲームは、実際にパフォーマー(作者自身)、もしくは鑑賞者がプレイすることによって仮想空間内での物理的な衝突など、インタラクティブな環境音が発生する仕組みになっている。発生した複数の「音」が重なり合うことによって、それらは偶発的な「音楽」となる。
サウンドはポストクラシカルや、現代のエクスペリメンタルミュージックに影響を受けている。我々が日常で耳にする機会が多い、リズム、メロディ、ハーモニーなどの要素を孕んだ西洋主義的な音楽から脱却し、新しい音楽の状態を作り上げた。
この作品を通して伝えたいストーリーのキーワードは、タイトルにもあるように「存在」「役割」である。私たちは生まれながらにして、組織、共同体などの中で役割を与えられ、その役割を担い、体現するコンテンツとして、社会における存在を認められているように感じる。しかし、ある人間が存在するということは、あらゆる自然科学の事象の組み合わせによってはじめて現前する、ある種の奇跡なのではないだろうか。
VRゲームのプレイを進めると、プレイヤーとアバター間の主従関係が徐々に崩壊していく。それは固定観念的な役割から一度解放させることで、「そこにいる、それだけで存在していることを肯定する」姿勢を表している。
従来のオーディオビジュアルのように形式化された、いわゆるクールなサウンド・ビジュアルとは異なり、その形式自体を問い直すようなこの作品は、一見生々しさや、いなたさを感じさせるだろう。しかし、それこそが「存在を肯定する」表象である。
これは、身体、音楽、映像、パフォーマンス、詩を複合的に組み合わせることによって、人間の存在について訴えかけるマルチメディア作品である。
この作品(ビジュアル×サウンド)のインスピレーション源は何ですか?
自分はメディアアートや映像を制作する以前から、DJやバンドのドラマーとして音楽活動をしていました。そのバックグラウンドを経て、映像やVRを制作するようになりました。最初はグラフィックスやMVといったビジュアルワークスだけでしたが、自分で音楽も作りたいと考え、オーディオパフォーマンスをするように至りました。また、ゲームのような3DCGのビジュアルは、海外のVJの影響もありました。日本のように音楽に完璧に当てはめられたモーショングラフィックスや、「わかりやすく」デザインされたVJが、自分の好みではないと感じていました。
その中で、2017~2019年のクラブやフェスに来日した海外のDJ/プロデューサーのVJに衝撃をうけました。そのVJは、日本人の感覚とは全く違うビジュアルを作り上げていました。3DCGを多用したリアルタイムエフェクト、実験映画のようなモンタージュなど。迫力のある映像はDJ/プロデューサーとともに「世界」を作り上げていました。
記憶に残っているのをリストアップします。
2017年
Aphex Twin × Weird Core at FUJIROCK’17
Arca × Jessy Kanda at FUJIROCK’17
Sinjin Hawke × Zora Jones Japan Tour 2017 at Circus Tokyo
2019年
KODE 9 × Lawrence Lek Live AV at WWW
011668 x S280F x vvxxii - LIVE & Installation at WWW
CORIN 【tamana MASSACRE】in K/A/T/O MASSACRE vol.249 at FORESTLIMIT
VJ以外からも多く影響を受けています。MUTEK.JP 2021のバーチャルギャラリーにも展示したSam RolefsやPussykrewなど。国内のアーティストだと、谷口暁彦さん、Komatsu Kazumichiさん (LIVE set)、浮舌大輔さんからも影響を受けています。そして、クラブやスペースで開催されるパーティーそのものからの影響も強く受けています。FORESTLIMITやWWWβは僕にとっての強いインスピレーションになっています。
VJ、ビジュアルアーティスト、そしてパーティーを含めて、これらの体験はすべて「世界」を感じることです。VRにおける没入する感覚は、自分自身の感覚が世界と溶け合う感覚です。自分がVRに面白さを感じ、それを使って表現活動をするのもすべてこの感覚があるからです。あらゆる現場での体験や、インプットしてきた映像などがインスピレーションの源になっています。
ビデオゲームとメタバースを意識して作りましたよね?
その通りです。ビデオゲームやメタバースからも強く影響を受けています。2Dの平面では体験することができない、3DCGの空間への没入の感覚こそ、自分にとっての表現の根幹を成しています。メタバースはどのようになっていくのかとても興味をもっています。いまはビジネスワードとして流行していますが、2010年前後からセカンドライフのように、既にメタバースは誕生していました。時代を経て、私たちはコロナの影響により日常生活が常にオンライン化し、その生活を拡張させるものがメタバースだと考えられています。
しかし、自分はアーティストとして、その社会の中でどのような変化が生まれ、どのように解釈し、どのように作品に昇華されるのかが問われていると思います。ビジネスとしてのメタバースを舞台に作品を作り上げるのではなく、一つの「世界」としてメタバースを作品に取り込めると面白いのではないかな、と私は考えています。
創作過程についてお聞きします。どのようなワークフローで、どのようなツールやソフトウェアを使ってこの作品を制作されたのでしょうか?
この作品は1年以上前から構想をしていました。VR・ゲームエンジンはマルチメディアとして活用できるソフトウェアのため、ビジュアルだけでなく、音楽も一緒にプログラミングできないかと考えていました。
その中で、ゲームエンジンによる「物理シミュレーション(例えば、球体がバウンスしたり、ぶつかったりするなど)」に面白さを感じました。ゲームエンジンによって物理シミュレーションを表現し、そこに「存在する」という見せ方と、音を組み合わせられるのではないかと思い、プロトタイプを2021年の夏に作りました。
現実世界でも物体と物体がぶつかり合うことによって音が発生するように、ゲームエンジン上でオブジェクトに物理シミュレーションをプログラミングし、物体通しがぶつかると、あらかじめ用意しておいたサウンドが発生する簡単なシステムを作りました。サウンドが発生するオブジェクトを複数用意し、それをプレイする人が楽器のように取り扱うことによって偶発的な音楽が生み出される仕組みとなっています。
ゲームエンジンはUnityを使用しています。細かい3DCGのオブジェクトはBlenderやPhotoshopなどを使用して制作しました。サウンド自体はNative InstrumentsのMaschine MK3を使用して制作しました。VRのビルドは、VRのプラットフォーム「STYLY」を使用しています。
VRは一人で体験するものであり、そのVRパフォーマンスを観客の前で披露することはナラティブ全体の重要な臨界点であると言えます。ここでは、通常のVR体験が意味するもの、つまりヘッドセットの外側では感情が共有されることのないパーソナルで親密な体験を解体しています。それについて説明していただけますか? なぜ観客と共有したのしょうか。
1つ目には「バーチャル」と「リアル」を並列にさせる試みです。その象徴として、アバターとプレイヤーの関係性を表現しています。紹介にもあるように、この作品はプレイヤーとアバターの間の主従関係を崩壊させることがテーマの一つにあります。ゲーム内にはプレイヤーであり、パフォーマーであり、作者のJACKSON kakiのアバターが登場します。プレイをすることによって、自分のパフォーマンスとゲームの2つに関係性が生まれます。
自分は過去の制作においても、バーチャルとリアルを並列する試みを行ってきました。今まではリアルとバーチャルは、主従関係にあると考えられてきました。リアルがバーチャルを操作している状態です。しかし、ポストインターネット以降の社会において、オンラインが常態化された生活において、はたしてバーチャルとリアルは主従関係なのか疑問に感じてました。
そしてコロナ以降は、もはや主従関係は崩壊し、バーチャルがリアルに影響を与える事象が起きることが増えたように感じられます。自分がバーチャルとリアルを並列させる試みは、その態度を示しています。
2つ目には、オーディオビジュアルの革新です。上記でも紹介しているように、多くのオーディオビジュアルは形式化されていると感じています。クールなカメラワークや、完全に音と同期されたエフェクトなど、とても作りこまれています。対して、自分のビジュアルはカメラワークや全体の世界観がチープであったり、いなたさを感じるものです。しかし、それこそが面白さであり、自分にとっての既存のオーディオビジュアルへのカウンターの姿勢でもあります。
人間の不完全さや、バーチャルリアリティの可能性など、さまざまな要素をマルチメディアとして解釈し落とし込むことで、VRをつかったオーディオビジュアルの革新性を見出しています。
MUTEK.JPでの体験はどうでしたか? パフォーマンスの出来には満足していますか?
自分の『存在している』をMUTEK.JPで披露できたことは、とても光栄です。MUTEKはメディアアート、テクノロジーアートの祭典であり、自分が尊敬するアーティストも出演していて、目標の一つでした。
また、自分は普段、キャパシティ100人規模のクラブやスペースで遊んだり、活動することが多いです。そこで培われたエクスペリメンタルとオルタナティブ精神を、オルタナティブな場所を超えて、オーバーグラウンドとアンダーグラウンドを繋ぐ場所で披露出来たことは、どちらのフィールドにとっても、とても有意義だったと考えています。『存在している』を鑑賞した人たちが、オーディオビジュアルとは何なのか、マルチメディアとは何なのか、VRとは何なのかと、考えるきっかけになったらとても嬉しいです。
また、自分は今後海外を視野に活動を考えています。MUTEKに出演した、というのは、海外への第一歩にもなったと思っています。
最後に、この作品を発展させる予定はありますか?
はい。この作品をアップデートしようと考えています。今回はパフォーマンスとしての作品でしたが、よりゲーム性を高めて、一般の人が遊べるようにしたいと考えています。そのためにはUI/UXの改良や、3DCGのクオリティアップ、サウンドバリエーションの増加などを考えてます。自分は将来的にはマルチメディアをテーマに、VR/ARやゲーム、メタバースといったメディアを中心に芸術作品を作り上げたいと考えています。2022年からは岐阜県にある情報科学芸術大学大学院、通称IAMASの学生になります。そこでマルチメディアと芸術に関する研究と制作を行い、将来的には「芸術家」になることを目指しています。
Interview conducted by Benoit Palop
ジャンルを超えて

創造の化学反応

没入体験の先端へ

Pro Conference: プログラムを公開